「障害者雇用の在宅求人を探しているけれど、なかなか見つからない」
「在宅で働きたいけれど、どうやって準備すればいいかわからない」
そんな悩みを抱えていませんか?
障害者の在宅求人は確実に存在しますが、多くの方が見つけられない理由があります。そして、求人サイトで探すだけでは解決できない根本的な課題があるのも事実です。
IT・クリエイティブ・事務に特化した就労継続支援B型事業所ドローンiでは、利用者の在宅ワーク実現をサポートしており、一般就労への道筋を築く支援を行っています。
本記事では「在宅求人が見つからない理由」や「在宅ワークを実現するための具体的な方法」の実践的なアプローチを詳しく解説します。
Contents
在宅求人が見つからない5つの理由
1. 専門スキルが不足している
障害者雇用の在宅求人の多くは、ITやデザイン、事務処理などの専門スキルを要求します。しかし、これらのスキルを持たない方が大半で応募要件を満たせないケースが非常に多いのが現状です。
具体的な問題点:
- パソコンの基本操作ができない
- Microsoft Office(Word、Excel、PowerPoint)が使えない
- Webデザインやプログラミングの知識がない
- データ入力や資料作成の経験がない
2. 求人情報の検索方法が限定的
多くの方が一般的な求人サイトのみで検索しているため、障害者向けの在宅求人を見逃しています。障害者雇用に特化した求人サイトや、就労支援機関が持つ独自の求人情報にアクセスできていないのが原因です。
見落としがちな求人情報源:
- 障害者雇用専門の求人サイト
- 就労移行支援・就労継続支援事業所のネットワーク
- 在宅就業支援団体が持つ求人情報
- 企業の直接的な障害者雇用枠
3. 自己PRと応募書類の準備不足
就職活動では面接はもちろんのこと、履歴書や職務経歴書での自己PRが重要になります。しかし、障害特性を活かした自己PRの書き方や、在宅ワークに適した経験・スキルのアピール方法を知らない方が多いのではないでしょうか。
よくある失敗例:
- 障害について触れるのを避けて、特性を活かせない
- 在宅ワークに関連する経験や適性を十分にアピールできない
- 具体的な成果物やポートフォリオを準備していない
- 自分の強みを明確に伝えられない
4. 面接や選考プロセスへの不安
在宅求人であっても選考プロセスは必要です。しかし、障害者の方の中には面接への不安や自分の障害について説明することへの抵抗感を持つ方が多く、応募を躊躇してしまうケースがあります。
選考における不安要素:
- オンライン面接の技術的な不安
- 障害の説明や配慮事項の伝え方
- 在宅ワークでの業務遂行能力の証明方法
- コミュニケーション能力の評価への不安
5. 継続的な就労への準備不足
在宅ワークは自己管理能力が特に大事になります。しかし、生活リズムの管理、業務の進捗管理、モチベーションの維持など、在宅ワークに必要な準備ができていない方が多いのが現状です。
在宅ワークで必要な準備要素:
- 規則正しい生活リズムの確立
- 集中できる作業環境の整備
- 自己管理とスケジュール管理のスキル
- 継続的な学習とスキルアップの習慣
求人サイトでは解決できない根本的問題
スキルと経験の不足という現実
障害者の在宅求人市場において最も深刻な問題は「求人はあるが、応募できる人材が少ない」という現実です。厚生労働省の調査によると、障害者雇用におけるテレワーク実施企業は約42.4%に上りますが、実際に障害者が応募できる求人は限られています。(参照:障害者のテレワーク支援に関する研究Ⅰ)
市場の現状:
- 在宅可能な障害者雇用求人は約3.2倍に増加(2020年比)
(参照:国内の企業においてテレワークで働く障害者の現状に関する研究) - しかし、応募要件を満たす障害者の数は追いついていない
- 特にIT・デザイン・事務分野での人材不足が深刻
単発的な求人探しの限界
求人サイトでの検索はその時点で公開されている求人情報に限られます。
しかしながら障害者の在宅ワーク市場は流動的であり、障害者が長期的に働いていくためには継続的な関係性や信頼関係の構築が必要な要素となります。
求人サイトの限界:
- 一時的な求人情報にしかアクセスできない
- 企業との継続的な関係構築ができない
- スキルアップや成長過程を企業に伝えられない
- 個別の配慮や調整が困難
支援体制の不足
在宅ワークを成功させるためには、就職前の準備から就職後の定着まで継続的な支援が必要です。しかし、求人サイトではこのような包括的な支援ができません。
必要な支援要素:
- 就労前のスキル習得支援
- 就職活動のサポート
- 就職後の定着支援
- 継続的なスキルアップ支援
- 企業との調整やフォローアップ
B型事業所とは?就労継続支援事業所の基本概要
就労継続支援B型事業所とは、障害や難病などにより一般企業での就労が困難な方を対象に働く機会と場所を提供する障害福祉サービスです。
障害のある方に対して生産活動などの機会を提供し、知識および能力の向上のために必要な訓練を行うことを目的としています。
B型事業所の主な特徴:
- 雇用契約を結ばない働き方
- 利用者の体調や状況に合わせた柔軟な勤務体制
- 作業を通じて得られる工賃の支給
- スキル習得と社会参加の機会提供
- 将来の一般就労に向けたステップアップ支援
A型事業所との違い
就労継続支援にはA型とB型があり、それぞれ異なる特徴を持っています。
| 比較項目 | A型事業所 | B型事業所 |
| 雇用契約 | あり | なし |
| 給与・工賃 | 最低賃金以上の給与 | 工賃(平均月額17,031円) |
| 対象者 | 雇用契約を結べる方 | 雇用契約が困難な方 |
| 利用期間 | 制限なし | 制限なし |
| 勤務時間 | 比較的安定した時間 | 柔軟な調整が可能 |
| 選考 | 面接などの選考あり | 選考なし |
A型事業所の特徴:
- 雇用契約に基づく労働のため労働基準法が適用される
- 最低賃金以上の給与が保障される
- 比較的安定した労働時間と勤務日数が設定される
- 一般企業により近い働き方
B型事業所の特徴:
- 雇用契約を結ばないため、より柔軟な働き方が可能
- 体調や障害特性に合わせた個別対応
- 工賃は事業所の収益に基づいて決定される
- より多様な障害状況の方が利用可能
障害者雇用との違い
また就労継続支援B型事業所と一般企業の障害者雇用には大きな違いがあります。
一般企業の障害者雇用:
- 企業と直接雇用契約を結ぶ
- 労働基準法に基づく給与・労働条件
- 基本的に週5日、1日8時間の勤務
- 企業の業務内容に従事
- 昇進・昇格の可能性
B型事業所:
- 福祉サービスとしての支援
- 工賃制度による収入
- 個別の体調や状況に合わせた勤務
- 訓練・スキル習得が主目的
- 将来の就労に向けた準備期間
B型事業所の利用条件
就労継続支援B型事業所は身体障害や知的障害、精神障害、発達障害などで一般企業での就労が困難と認められる方が対象になります。年齢は原則18歳以上で上限制限はありません。
利用条件は自治体や事業所によって柔軟に対応されることがあるため、詳細は地域の障害福祉窓口での確認が推奨されます。
工賃制度について
B型事業所では、雇用契約を結ばない代わりに「工賃」が支払われます。工賃は、事業所が行う生産活動によって得た収益から、必要な経費を差し引いた額を利用者に分配するものです。
令和4年度の就労継続支援B型事業所の平均工賃は月額17,031円となっています。(参照:厚生労働省工賃実績)
ただし、事業所や作業内容により大きく異なり、月額数千円から10万円以上まで幅があります。IT・クリエイティブ分野などの専門性の高い作業を行う事業所では、より高い工賃を実現している場合があります。
各種給付金・雇用状況との併用について
就労継続支援B型事業所を利用する際、現在受給している各種手当や雇用状況によって、利用可能性や注意点が異なります。ここでは、主要なケースについて詳しく解説します。
傷病手当金受給中の利用:基本的に可能
傷病手当金受給中でも就労継続支援B型事業所の利用は可能です。B型は雇用契約がない非雇用型であり、訓練やリハビリ目的での利用は認められています。
ただし傷病手当は「労務に服することができない」状態が前提のため、長時間の利用は「労務に服することができる」と判断され、支給停止の可能性があります。 主治医の意見書が必要な場合も多く、詳細は主治医と地域の障害福祉窓口へ相談しましょう。
失業保険受給中の利用:可能
失業保険を受給しながら就労継続支援B型事業所を利用するのは可能です。ただし、失業保険の受給条件は「就職の意思と能力がある」ことが前提となります。
失業保険に関しては地域のハローワークが管轄になりますので、必ずB型事業所利用についてはハローワークに報告・相談をしましょう。
障害者雇用での時短勤務中の利用:令和6年度より条件付きで可能
令和6年4月1日の制度改正により、一般就労をしながら就労継続支援B型事業所の利用が可能になりました。具体例としては、「週3日企業勤務(1日4時間)+ 週2日B型事業所利用」や「午前中は企業勤務、午後はB型事業所での訓練」などの例があげられます。
勤務先企業の同意が必要なケースもあり、最終的に市区町村が併用の可否を判断するので、まずは地域の障害福祉窓口へ相談しましょう。
障害年金との併用:問題なく併用可能
障害年金とB型事業所の併用は基本的に問題ありません。障害年金を受給しながらB型事業所を利用するのは一般的であり、収入の安定や社会参加のメリットがあります。
ただし20歳前障害による障害基礎年金のケースでは、所得制限があるため工賃との合計額に注意をする必要があるため、詳しくは地域の年金事務所や障害福祉窓口へ相談しましょう。
B型事業所による段階的支援アプローチ
就労継続支援B型事業所は障害者の就労支援において重要な役割を果たしています。特に在宅特化型のB型事業所では自宅にいながら職業訓練を受け、実際の業務経験を積めます。
B型事業所の在宅支援の優位性:
- 通所の必要がないため、体調や障害特性に配慮できる
- 個別のペースで学習・訓練を進められる
- 実際の業務を通じて経験を積める
- 工賃を得ながらスキルアップできる
- 就労移行への橋渡し役となる
ドローンiの支援内容
IT・クリエイティブ・事務に特化した就労継続支援B型事業所「ドローンi」では、利用者の現在のスキルレベルに応じて包括的な支援を提供しています。
基礎スキル習得支援:
- タイピング練習とパソコン基本操作の指導
- Microsoft Office(Word、Excel、PowerPoint)の習得支援
- 在宅ワークに必要な基本的なデジタルリテラシー
専門スキル習得支援:
- プログラミング(オンライン学習ツールを活用)
- グラフィックデザイン(Photoshop、Illustrator)
- 動画編集(各種編集ソフトの使用方法)
- Webデザインやコンテンツ制作
実践業務支援:
- 実際のプロジェクトへの参加機会
- クライアントワークの経験
- チームでの作業経験
- 品質管理と納期管理の実践
就労準備支援:
- ポートフォリオの作成支援
- 面接対策と自己PR準備
全国対応の在宅支援体制
ドローンiは全国どこからでも利用できる在宅特化型の支援体制を構築しています。この体制により地域による支援格差を解消し、より多くの障害者に在宅ワークの機会を提供しています。
効果的なスキル習得
ドローンiでは利用者一人ひとりの学習ペースや、理解度に合わせた個別指導を実施しています。集団指導では困難なサポートにより、効率的なスキル習得を実現しています。
個別指導の特徴:
- 利用者の理解度に合わせた進度調整
- 苦手分野の重点的なサポート
- 得意分野の更なる伸長
- 学習方法の個別カスタマイズ
- 継続的なモチベーション管理
実案件参加によるリアルな業務経験
スキル習得後は実際のクライアントからの案件に参加し、リアルな業務経験を積めます。この経験は就職後の業務遂行能力の向上だけでなく、自信の向上にもつながります。
実案件参加のメリット:
- 実際の業務フローの理解
- クライアントとのコミュニケーション経験
- 品質基準と納期管理の実践
- チームワークの経験
- 実績の蓄積とポートフォリオ作成
工賃制度による経済的支援
就労継続支援B型事業所では、訓練を受けながら工賃を得ることができます。ドローンiでは、利用者のスキルレベルに応じて、より高い工賃を目指せる制度を整備しています。
工賃制度の特徴:
- スキルに応じた工賃設定
- 実案件参加による高工賃の実現
- 成果に基づく評価システム
- 継続的な工賃向上の機会
- 経済的自立への段階的な支援
成功事例と具体的な成果
ドローンiはこれから2025年9月に新規オープンの就労継続支援B型事業所です。
関連会社では、既に多くの利用者が在宅ワークのスキルを習得し一般就労を実現しています。
事例1: 「あにゃんぐ!」さんの成功ストーリー
- 利用期間: 6ヵ月
- 習得分野: 動画編集・デザイン業務
- 就職後: スキル支援員として他の利用者の指導にも参加
事例2: 「ちぢれストレート」さんの成功ストーリー
- 利用期間: 7ヵ月
- 習得分野: 社外コンサルやマーケティング
- 就職後: 採用業務(中途・新卒)も担当
利用開始までの流れ
申込みから利用開始まで
Step 1: 初回相談(無料) ドローンi個別説明会にて、サービス内容の詳細説明と個別相談を実施します。
- サービス内容の詳細説明
- 現在の状況とご希望のヒアリング
- 利用可能性の確認
- 質問・相談への回答
Step 2: 体験利用 実際のサービスを体験していただき、相性を確認します。
- 基本的な訓練の体験
- オンライン環境の確認
- 他の利用者との交流
- 支援員との相性確認
Step 3: 利用契約 体験利用後、継続利用を希望される場合は正式な契約を行います。
- 個別支援計画の策定
- 利用目標の設定
- 利用期間の確認
- 必要な手続きの完了
Step 4: 本格的な支援開始 個別支援計画に基づいて、本格的な訓練と支援を開始します。
- 基礎スキルの習得開始
- 定期的な進捗確認
- 必要に応じた計画調整
- 継続的なサポート
利用の条件と準備
利用条件:
- 障害者手帳をお持ちの方
- 在宅での訓練参加が可能な方
- パソコンとインターネット環境をお持ちの方
- 継続的な利用が可能な方
必要な準備:
- 障害者手帳の準備
- パソコン環境の整備
- インターネット接続環境の確認
- 静かな作業環境の確保
在宅ワーク成功のための重要なポイント
発達障害の方の在宅ワーク適性
発達障害のある方にとって、在宅ワークは多くのメリットがあります。自分のペースで作業ができて環境による刺激を調整できるため、集中力を最大限に発揮することが可能です。
発達障害の方の在宅ワーク成功要因:
- 感覚過敏への配慮ができる環境
- 自分のリズムでの作業進行
- 集中できる静かな環境の確保
- 詳細な作業手順の明確化
うつ病・双極性障害・統合失調症からの復職と在宅ワーク
うつ病などの精神障害から復職を目指す方にとって、在宅ワークは段階的な社会復帰の手段として有効です。リモートでの在宅ワークは通勤ストレスがなく、体調に合わせた勤務が可能です。
うつ病・双極性障害・統合失調症の方の在宅ワーク準備:
- 規則正しい生活リズムの確立
- 段階的な作業負荷の調整
- ストレス管理スキルの習得
- 継続的なメンタルヘルスケア
IT分野での障害者雇用の可能性
IT業界は障害者雇用において大きな可能性を秘めています。テクノロジーの発展により、多様な働き方が実現可能になり、障害者の特性を活かせる職種が増加しています。
IT分野での障害者雇用のメリット:
- 在宅勤務が可能な職種が多い
- 個人の技術力が評価される
- 継続的なスキルアップが可能
- 高い給与水準が期待できる
- 多様な働き方に理解のある企業が多い
まとめ:確実な在宅ワーク実現への道筋
障害者の在宅求人は確実に存在し需要も高まっています。
しかし、単に求人サイトで探すだけでは多くの障害者の方が抱える根本的な課題の解決はできません。
重要なのは、段階的なスキル習得と継続的な支援体制です。就労継続支援B型事業所ドローンiのような専門機関を活用すれば、下記のように着実に自身に合った仕事の就業へ進めます。
- 基礎から専門まで体系的なスキル習得
- 実案件参加による実践経験の積み重ね
- 個別の障害特性に配慮したサポート
- 就職に向けた総合的な準備支援
在宅ワークは障害者の方にとって理想的な働き方の一つです。
通勤の負担がなく自分に合った環境で能力を発揮できる在宅ワークは、多くの障害者にとって新しい可能性を開く働き方といえるでしょう。
しかしその実現には適切な準備と支援が不可欠です。スキル習得から就職活動まで、包括的なサポートを受けることで、在宅ワークでの就労を実現ができます。
もし、あなたが在宅ワークでの就労を真剣に考えているなら、まずは専門機関への相談から始めてみてください。ドローンiでは、あなたの現在の状況や希望に合わせた個別の支援計画を提案し在宅ワークへの実現を支援します。
今すぐ行動を起こしましょう。
在宅ワークでの自立した生活は、決して夢ではありません。適切な支援があれば、必ず実現可能です。まずは、ドローンiの個別説明会にお申し込みください。
あなたの新しいキャリアが、ここから始まります。
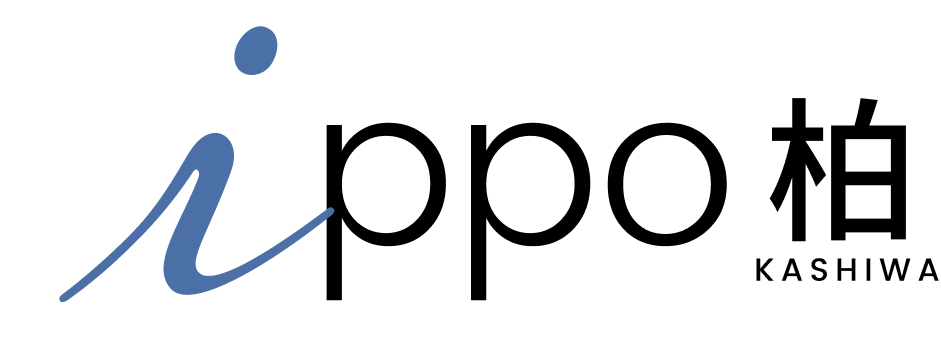







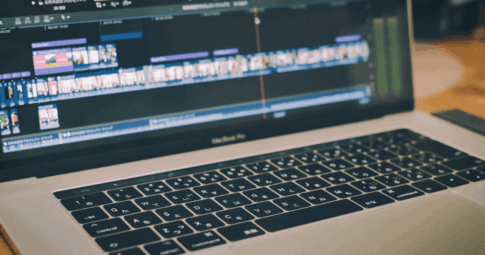


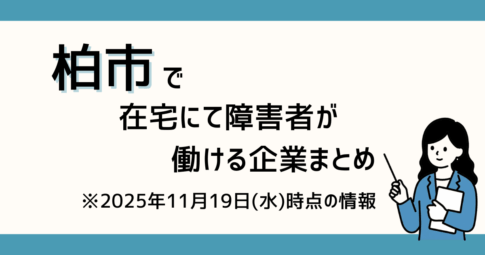
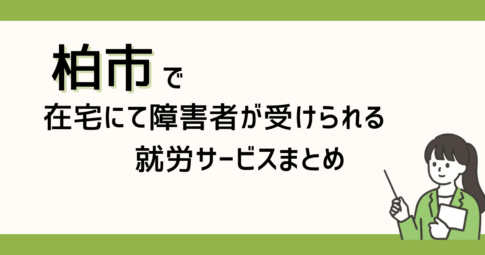
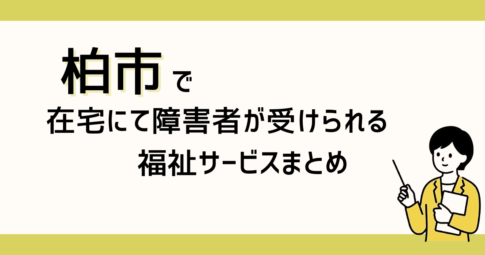
コメントを残す