発達障害のある方の多くが「自分に合った仕事が見つからない」「職場で理解されず孤立してしまう」などの悩みを抱えています。
発達の特性は人により差はあれ、多くの人が持っており日常生活に支障がなければ障害とは診断されません。しかし、その特性が社会生活を送る上で著しい困難をもたらしていると発達障害と診断されます。
こうした困難の多くは、特性と職場環境が合っていないために生じているのです。
本記事では、自分に合った働き方を見つけるための具体的な方法をご紹介します。
Contents
発達障害の3つの種類と特性
発達障害は生まれつきの脳機能の発達のアンバランスさと、その人が過ごす環境との相性の悪さから、社会生活に困難が生じる障害です。
主な種類として、ADHD、ASD、LDの3つがあり、それぞれ異なる特性を持っています。
これらの特性を理解すれば、自分に合った仕事を見つける第一歩となります。
ADHD(注意欠如・多動症)の特性
ADHDは「不注意性」「多動性」「衝動性」の特性を持つ発達障害です。
不注意性では忘れ物やケアレスミスが多く、注意が散漫になりやすい傾向があります。整理整頓や時間管理も苦手で、物をなくしたり約束を忘れたりする場面も少なくありません。
多動性・衝動性の面では、じっとしていられず、思いついた内容をすぐに口にしてしまったり、後先考えずに行動してしまったりする特徴が見られます。
これらの特性はすべての人に現れるわけではなく、いずれかまたは複数の特性から困難が生じるケースが多いです。
一方で、興味のある分野には高い集中力を発揮したり、新しいアイデアを生み出す創造性に優れていたりする強みもあります。
ASD(自閉スペクトラム症)の特性
ASDはコミュニケーションや対人関係に困難が生じる点を特徴とする発達障害です。かつてのアスペルガー症候群、自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害などが統合された診断名です。
主な特性として、言葉を文字通りに受け取ってしまい、暗黙のルールや曖昧な表現の理解が難しい点が挙げられます。特定の物事へのこだわりも強く、予定の変更や環境の変化に対して強い不安を感じる場合があります。
さらに、感覚過敏も特徴的で、音や光、触覚などに対して過度に敏感、あるいは鈍感に反応します。
一方で、ルールを守る姿勢が真面目で、細部への注意力が高く、特定の分野で専門的な知識を深める能力に優れている強みもあります。
LD(学習障害)の特性
LD(学習障害/限局性学習障害)は、読む・書く・計算する・推論するなど、特定の学習行為のみに困難が生じる発達障害です。全般的な知的発達に遅れはないものの、ごく一部の事柄に顕著な困難が現れる点が大きな特徴です。
具体的には、読字障害(ディスレクシア)では文字を読むのが困難で、文章の理解に時間がかかります。書字表出障害(ディスグラフィア)では、文字を書いたり文章を構成したりする際に苦労します。算数障害(ディスカリキュリア)では、数の概念の理解や計算、数式の処理が難しくなります。
これらの困難は怠けや努力不足によるものではなく、脳機能の特性から生じるものです。
一方で、口頭でのコミュニケーション能力が高かったり、視覚的な情報処理が得意だったりするなど、他の能力は十分に備わっています。
ASDの3つのパターン
ASDの特性は一律ではなく、対人関係やコミュニケーションの取り方によって大きく3つのパターンに分類されます。
積極奇異型は人に積極的に働きかけるものの周囲から浮いてしまうタイプ、受動型は受け身の姿勢で自己主張が弱いタイプ、孤立型は他者との関わりを求めず自分の世界で過ごすタイプです。
それぞれのパターンによって、職場で直面する困難や必要な配慮が異なります。自分がどのパターンに近いかを理解すれば、より適した働き方や職場環境を選べます。
積極奇異型
積極奇異型は、人に積極的に働きかけるものの、周囲から浮いてしまうタイプのASDです。
自分のルールに基づいて積極的に他者と関わろうとするため、一見すると社交的に見える場合もあります。しかし、相手の反応や状況を読み取るのが苦手なため、一方的な関わり方になりがちです。自分のこだわりや興味のある内容を相手の都合を考えずに話し続けてしまったり、自分のルールを押し付けてしまったりする様子が多く見られます。
職場では、自分の意見を長々と話してしまい会議時間が延びる、相手の忙しさに気づかずに話しかけてしまうなどの困難が生じやすいです。
一方で、熱意があり、興味のある分野には情熱を持って取り組める強みがあります。
受動型
受動型は、受け身の姿勢で自己主張が弱く、周囲の意見や状況に流されやすいタイプのASDです。表面上は奇妙さが少なく目立ちにくいため、周囲から「おとなしい人」「控えめな人」と思われる傾向があります。
自分の意見や希望を伝えるのが苦手で、相手に合わせすぎてしまいます。そのため職場では理不尽な業務を押し付けられたり、他者に利用されたり、支配・搾取されるリスクが高くなります。
自分の限界を超えても我慢してしまい、気づいたときには心身ともに疲弊しているケースも少なくありません。
一方で、協調性があり、指示された内容を真面目に取り組む姿勢は職場で評価されやすい強みです。
孤立型
孤立型は、まるで他者が存在しないかのように、自分の世界の中で生きるタイプのASDです。他者との関わりを積極的に求めず、基本的に一人で過ごす時間を好みます。
自身の好みや服装に独特さがあり、それが目立つ場合がありますが、本人は周囲の目をあまり気にしません。雑談を特に苦手とし、業務上必要最低限のコミュニケーション以外は避ける傾向があります。
職場では「付き合いが悪い」「協調性がない」と誤解されやすく、孤立してしまう場合があります。
しかし、一人で黙々と作業する能力に優れており、集中力が高く、周囲に左右されずに自分のペースで業務を進められる強みがあります。対人関係のストレスが少ない環境であれば、その能力を十分に発揮できます。
発達障害がある方が仕事で直面する4つの困りごと
発達障害のある方が職場で抱える困りごとは多岐にわたりますが、特に多く見られるのが「仕事が続かない」「ミスを繰り返す」「コミュニケーションがうまく取れない」「指示が理解できない」などの課題です。
これらの困りごとは本人の努力不足や怠けによるものではなく、発達障害の特性と職場環境が合っていないために生じています。
ここではこれらの困りごとがなぜ起きるのかその原因と具体的な状況について、詳しく見ていきます。
仕事が続かない・転職を繰り返してしまう
発達障害のある方の中には、短期間で離職を繰り返してしまうケースが少なくありません。この背景には、職場環境と自分の特性が合っていない点が大きく影響しています。
ADHDの特性がある場合、ルーティンワークに飽きてしまったり、興味が移りやすく一つの仕事に集中できなかったりする傾向があります。
ASDの特性がある場合は、暗黙のルールや職場の人間関係が理解できず、孤立してしまうのが離職の原因です。感覚過敏により職場の音や光がストレスとなり、継続が困難になるケースもあります。
さらに適切な配慮を受けられない環境では日々のストレスが蓄積し、二次障害としてうつ病や適応障害を発症してしまう場合もあります。
ミスを繰り返してしまい自信を失う
仕事でのミスが多く何度注意されても同じ失敗を繰り返してしまう悩みは、発達障害のある方によく見られます。
ADHDの不注意性により、確認作業を怠ってしまったり細かい部分を見落としてしまったりするケースが典型的です。複数の業務を同時に抱えるマルチタスクの状況では、優先順位がつけられず混乱してしまう場合もあります。
LDの特性がある場合、数字の入力や書類作成で特定の箇所だけ繰り返しミスをしてしまいます。
こうしたミスは本人の努力不足ではなく、脳機能の特性から生じているにも関わらず、周囲からは「注意力が足りない」と誤解されやすいです。
繰り返し叱責されると自己肯定感が低下し自信を失ってしまいます。
コミュニケーションがうまく取れず孤立する
職場での雑談や暗黙のルールが理解できず、人間関係に悩む発達障害のある方は多く存在します。
ASDの特性により言葉を文字通りに受け取ってしまうため、冗談や皮肉が理解できず、場違いな反応をしてしまう場合があります。相手の表情や声のトーンから感情を読み取るのも苦手なため、相手が不快に感じているサインに気づけない場合もあります。
ADHDの衝動性により、相手の話を最後まで聞かずに自分の話を始めてしまったり、思った内容をそのまま口にしてしまったりする様子も少なくありません。
こうした行動が「協調性がない」「変わった人」と誤解され、職場で孤立してしまうケースが多く見られます。
指示や業務内容が理解できず混乱する
口頭での指示が覚えられない、曖昧な指示では何をすればいいかわからないなどの困りごとも、発達障害のある方に多く見られます。
ADHDの特性により、複数の指示を一度に受けると忘れてしまう傾向があります。
ASDの特性がある場合、「適当に」「いい感じで」などの抽象的な指示では具体的に何をすればいいのか判断できず立ち止まってしまいます。
LDの特性により、文字で書かれたマニュアルを読んで理解するのが難しいケースもあります。業務の優先順位をつけるのが苦手で、どれから手をつければいいかわからず混乱してしまう場合もあります。
こうした状況で何度も質問すると「何度も同じ内容を聞く」「理解力がない」と思われる不安から、わからないまま作業を進めてミスにつながってしまいます。
発達障害の特性を活かせる仕事と職場環境を種類別に解説
発達障害のある方にとって、自分の特性に合った仕事を選ぶのは非常に大切なポイントになります。苦手な部分に焦点を当てるのではなく、得意な特性を活かせる職種や環境を選べば、能力を十分に発揮しながら長く働き続けられます。
ADHD、ASD、LDそれぞれの特性によって、向いている仕事の種類や働きやすい職場環境は異なります。
ここでは各発達障害の種類別に、具体的な職種例と働きやすい環境の条件を詳しく解説します。自分の特性を理解したうえで、適した仕事を見つける参考にしてください。
ADHD(注意欠如・多動症)の特性を活かせる仕事と職場環境
ADHDの特性がある方は、創造性や発想力、行動力を活かせる仕事に適性があります。具体的な職種としては、企画・広報、クリエイター、営業職、イベントプランナーなどが挙げられます。
新しいアイデアを生み出したり変化に富んだ業務内容に取り組んだりする場面で、ADHDの方の強みが引き出されます。一方で、細かいデータ入力や長時間同じ作業を繰り返すルーティンワークは苦手とする傾向があります。
働きやすい環境としては、業務内容に変化がある職場、短いスパンで成果が見える仕事、視覚的にタスクを管理できるツールが使える環境が適しています。
静かすぎる環境よりも適度に活気のある空間の方が集中しやすい場合もあります。さらに、フレックスタイム制度やリモートワークなど、柔軟な働き方ができる職場も相性が良いです。
ASD(自閉スペクトラム症)の特性を活かせる仕事と職場環境
ASDの特性がある方は、ルールが明確で一人で集中して取り組める仕事に適性があります。具体的な職種としては、プログラマー、データ入力、校正・校閲、研究職、品質管理などが挙げられます。
特定の分野に深い知識を持ち、細部まで正確に作業できる能力はASDの方の大きな強みです。一方で、臨機応変な対応が求められる接客業や、頻繁に予定が変わる業務は苦手とする傾向があります。
働きやすい環境としては、業務手順がマニュアル化されている職場、静かで刺激の少ない空間、対人コミュニケーションが最小限で済む環境が適しています。
指示が具体的で明確に伝えられる職場、予定変更が少なく安定したスケジュールで働ける環境も良いでしょう。
LD(学習障害)の特性を活かせる仕事と職場環境
LDの特性がある方は、苦手な分野を避けて得意な能力を活かせる仕事を選びましょう。
読字障害がある場合は、口頭でのコミュニケーションや視覚的な情報処理が中心となる職種、例えば接客業、デザイナーなどが向いています。書字障害がある場合は、手書きではなくパソコンを使った業務、例えばプログラマーやデータ分析など、タイピングで完結する仕事が適しています。算数障害がある場合は、数字の処理が少ない職種を選ぶのが望ましいです。
働きやすい環境としては、読み上げソフトや音声入力などの支援ツールが使える職場、業務内容を視覚的に確認できる仕組みがある環境が良いでしょう。
苦手な部分を周囲がサポートしてくれる協力的なチーム体制があると、LDの方は持ち前の能力を十分に発揮できます。
自分に合った仕事を見つけるための3つのステップ
発達障害の特性を理解したうえで、実際に自分に合った仕事を見つけるためには、具体的なステップを踏むのが大切です。
まず自分の得意・苦手を整理し、次に働き方の選択肢を知り、そして職場環境や企業文化をリサーチする、3つのステップが効果的です。
これらのステップを丁寧に進めれば、特性との相性の悪さを減らし長く働き続けられる職場を見つける可能性が高まります。自己分析から始めて自分らしい働き方を具体的にイメージしていけば、就職・転職活動を成功させる鍵となります。
ここではそれぞれのステップで何をすべきか、具体的な方法とポイントを詳しく解説します。
自分の得意なこと・苦手なことを整理する
仕事探しの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握する作業です。得意な内容、苦手な内容、ストレスを感じる状況、集中できる環境などを書き出してみましょう。
例えば「一人で黙々と作業するのが得意」「複数の業務を同時に抱えると混乱する」「口頭での指示は忘れやすい」などの具体的な項目を挙げていきます。この作業は「自分の取扱説明書」を作るイメージで行うと効果的です。
過去の仕事でうまくいった経験、逆につまずいた経験を振り返りましょう。就労移行支援事業所や発達障害者支援センターでは、専門スタッフと一緒に自己分析を行うプログラムも提供されています。客観的な視点を取り入れれば、自分では気づかなかった強みや配慮が必要な点が明確になります。
働き方の選択肢を知る(一般雇用・障害者雇用・在宅など)
発達障害のある方の働き方には、主に一般雇用、障害者雇用、在宅ワークの選択肢があります。
一般雇用は障害を開示せずに働く方法で職種や企業の選択肢が広い一方、配慮を受けにくいデメリットがあります。
障害者雇用は障害を開示して働く方法で、障害のある方が能力を発揮できるように事業者が過度な負担なく行う調整や工夫である合理的配慮を受けやすく、職場の理解が得られやすいメリットがあります。ただし職種が限定される場合や、給与水準が一般雇用より低くなる傾向がある点も理解しておく必要があります。
2024年4月からは民間事業者にも合理的配慮の提供が法的義務化されたため、障害者雇用での環境整備が進んでいます。
在宅ワークやフリーランスの働き方も、通勤や対人ストレスを軽減できる選択肢です。
それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、自分の特性や状況に合った働き方を選ぶのが重要です。
職場環境や企業文化をリサーチする
自分に合った職場を見つけるためには求人票の情報だけでなく、職場環境や企業文化を事前にリサーチする必要があります。具体的には企業のホームページやSNS、口コミサイトなどで、社風や働き方の実態を確認しましょう。
障害者雇用の実績があるか、ダイバーシティ推進に取り組んでいるか、合理的配慮の事例が紹介されているかなども重要なチェックポイントです。
可能であれば、面接時に職場見学をお願いして、実際の雰囲気や業務環境を確認するのも有効です。オフィスの照明の明るさ、騒音レベル、座席配置、休憩スペースの有無など、感覚過敏への配慮が必要な方にとっては特に重要な情報となります。
転職エージェントや就労移行支援事業所を活用すれば、企業の内部情報や過去の定着実績など、個人では得にくい情報を提供してもらえます。
事前のリサーチを丁寧に行えば、入社後の相性の悪さを防げます。
発達障害がある方が仕事を長く続けるための5つの工夫
発達障害のある方が職場で直面する課題は、適切な工夫と対処法を身につければ克服できる可能性があります。
これらの対処法は自分一人で抱え込むのではなく、職場の理解と協力を得ながら実践すれば、より効果を発揮します。職場に定着し長く働き続けるためには、日々の業務の中で実践できる具体的な工夫が必要です。
ここでは実際に多くの発達障害のある方が実践している5つの工夫を紹介します。
「コミュニケーションの取り方」「合理的配慮の依頼」「ツールを活用したミス防止」「ストレスマネジメント」そして「信頼できる相談先の確保」です。
これらの工夫は単独で行うよりも組み合わせて実践すれば、より高い効果を発揮します。完璧を目指すのではなく少しずつ自分に合った方法を取り入れていけば、長期的な職場定着につながります。
コミュニケーションの課題を克服する工夫
職場でのコミュニケーションを円滑にするためには、いくつかの具体的な工夫が有効です。
まず口頭での指示を受けたら必ずメモを取り、理解した内容を復唱して確認する習慣をつけましょう。曖昧な指示を受けた場合は、「具体的には○○という理解で合っていますか」と質問して明確にしましょう。
自分の考えを伝える際には、結論→理由→具体例→結論の順で話すPREP法を意識すると、相手に伝わりやすくなります。
メールやチャットツールを活用して、文字でのやり取りを増やすのも効果的です。雑談が苦手な場合は、無理に参加しようとせず、業務に関する会話で信頼関係を築いていく方法もあります。
職場の上司や同僚に、自分のコミュニケーションの特性を事前に伝えておけば誤解を防ぎ、理解を得やすくなる場合もあります。
職場での合理的配慮を適切に依頼する
2024年4月から民間事業者にも合理的配慮の提供が法的義務化されました。これにより、発達障害のある方が職場で必要な配慮を求めやすくなっています。
配慮を依頼する際は、「事実」と「代替案」をセットで具体的に伝えるのが良いでしょう。
例えば「口頭での指示を覚えるのが難しい(事実)ので、指示をメールやチャットで送っていただけますか(代替案)」といった形で伝えましょう。
感覚過敏がある場合は「オフィスの音が気になって集中しにくい(事実)ので、イヤーマフの使用を許可していただけますか(代替案)」のように依頼します。
配慮を求める行為は決してわがままではなく、自分の能力を最大限発揮するために必要な調整であると理解するのが大切です。配慮を受けた後はその効果や感謝の気持ちを上司に伝えれば、より良い関係を築けます。
メモやツールを活用してミスを減らす
発達障害の特性によるミスを防ぐためには、記憶や注意力に頼るのではなくツールを積極的に活用するのが有効です。
ToDoリストアプリ(Todoist、Microsoft To Do、Notionなど)で業務を可視化し、完了したタスクにチェックを入れていく習慣をつけましょう。スマートフォンのリマインダー機能やアラームを使って、締切や会議の時間を通知するように設定します。
自分専用の業務マニュアルを作成し、手順を確認しながら作業を進めればミスを減らせます。
ダブルチェックの仕組みを取り入れるのも効果的で、上司や同僚に確認を依頼したり時間を置いて自分で再確認したりする方法があります。
電子機器の活用だけでなく、付箋やホワイトボードなど、アナログのツールも自分に合ったものを選んで使い分けましょう。
ストレス対処法を実践し、二次障害を予防する
発達障害のある方は、日常的に多くのストレスを抱えやすく適切に対処しないと二次障害(うつ病、適応障害、不安障害など)を発症するリスクがあります。
ストレスコーピング(対処法)を複数持っておくと良いでしょう。例えば、散歩、音楽鑑賞、アロマ、瞑想アプリの利用など、自分に合ったリラックス方法を見つけましょう。
完璧主義を手放し、60~80%の完成度で十分な場合が多いと理解するのも大切です。
睡眠の質を確保すれば心身の健康維持に欠かせません。規則正しい生活リズムを保ち、十分な休息を取るよう心がけてください。
体調不良や強いストレスを感じたときは、無理をせず休暇を取るのも必要です。早めに医療機関を受診し専門家の支援を受ければ、二次障害の予防や早期回復が可能です。
信頼できる相談先を確保しておく
仕事の悩みや困りごとを一人で抱え込まず、相談できる相手や機関を確保しておきましょう。
職場内では、直属の上司や人事担当者、産業医など、理解のある相談相手を見つけておくと安心です。
職場外では、発達障害者支援センターや障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センターなどの公的機関が利用できます。就労移行支援事業所を利用して就職した場合は、就職後も定着支援を受けられるため困ったときに相談できる心強い存在です。
転職エージェントの中には、就職後もフォローを提供しているところもあります。同じ発達障害のある当事者コミュニティやピアサポートグループに参加すれば、共感や情報交換ができ孤独感を軽減できます。
複数の相談先を持てば、状況に応じて適切な支援を受けられる体制を整えられます。
FAQ
Q. 発達障害があると診断されたら、必ず障害者雇用で働くべきですか?
発達障害の診断を受けたからといって、必ず障害者雇用で働かなければならないわけではありません。一般雇用と障害者雇用のどちらを選ぶかは、本人の特性の程度、必要な配慮の内容、キャリアの希望などによって判断すべきです。
一般雇用のメリットは、職種や企業の選択肢が広く給与水準も比較的高い傾向がある点です。ただし障害を開示しないため配慮を受けにくく、困難を一人で抱えるリスクがあります。
障害者雇用のメリットは、職場の理解が得られやすく合理的配慮を受けながら働けるため、長期的な職場定着につながりやすい点です。ただし、職種が限定される場合があり、給与水準が一般雇用より低くなる傾向もあります。
自分の特性や必要な配慮の程度を考慮し、就労支援機関や転職エージェントと相談しながら、自分に合った働き方を選択しましょう。
Q. 仕事でミスが多いのですが、これは発達障害のせいでしょうか?
仕事でミスが多いからといって、必ずしも発達障害があるとは限りません。ミスの原因には、業務の理解不足や経験不足、疲労、ストレス、職場環境など、さまざまな要因が考えられます。
ただし特定のパターンでミスが繰り返される場合、発達障害の特性が関係している可能性もあります。例えば「注意力の問題で細かい部分を見落とす」「複数の業務を同時に抱えると混乱する」「口頭での指示を忘れてしまう」などのミスが頻繁に起きる場合は、ADHDの特性が影響しているかもしれません。数字の入力だけ繰り返しミスをする場合は、LDの可能性も考えられます。
気になる場合は精神科や心療内科で相談してみるのをおすすめします。診断の有無に関わらず、ミスを減らすための具体的な対処法(メモを取る、ダブルチェックをする、ツールを活用するなど)を実践すれば、業務の質を改善できる可能性があります。
Q. 感覚過敏があり、職場の音や光がストレスです。どう対処すればいいですか?
感覚過敏による職場でのストレスは、適切なツールと環境調整で軽減できます。
聴覚過敏がある場合は、イヤーマフやノイズキャンセリングイヤホンを使用して、周囲の雑音を遮断しましょう。視覚過敏がある場合は、サングラスやブルーライトカットメガネを活用する、デスクの照明を調整する、パソコンの画面輝度を下げるなどの対策が有効です。触覚過敏がある場合は、肌に優しい素材の衣服を選ぶ、タグを切り取るなどの工夫が役立ちます。
職場に静かな休憩スペースがあれば、過剰な刺激を受けたときに一時的に避難できる場所として活用しましょう。上司や人事担当者に感覚過敏について説明し、座席の配置変更(窓際や奥の席など)、フレックスタイム制度の利用(通勤ラッシュを避ける)などの合理的配慮を依頼するのも検討してみてください。
Q. 二次障害とはなんですか?予防する方法はありますか?
二次障害とは、発達障害の特性そのものではなく特性による困難や周囲の理解不足によって二次的に生じる心身の不調です。
具体的には、うつ病、適応障害、不安障害、パニック障害、睡眠障害などの精神面の不調や、頭痛、胃痛、倦怠感などの身体面の不調が含まれます。二次障害は、職場でのストレス、失敗体験の積み重ね、孤立感、自己肯定感の低下などが原因で発症します。
予防するためには、まず自分の特性を理解し適切な対処法を身につけるのが重要です。職場で合理的配慮を求める、ストレスコーピングを実践する、十分な睡眠と休息を取る、信頼できる相談先を確保しておくのも効果的です。
無理をせず自分のペースで働ける環境を選ぶのも大切です。もし二次障害の兆候(気分の落ち込み、不眠、食欲不振など)が現れたら、早めに医療機関を受診し、専門家の支援を受けるのが回復への近道です。
Q. 発達障害のある方が利用できる就労支援サービスにはどのようなものがありますか?
発達障害のある方が活用できる就労支援サービスとしては下記があります。
1. ハローワーク(障害者専用窓口):障害者雇用の求人紹介、職業相談、精神・発達障害者雇用サポーターによる専門支援を無料で提供。障害者トライアル雇用事業も利用可能です。
2. 障害者就業・生活支援センター:就労面と生活面の両方から総合的に支援。就職準備、職場実習、就職活動の同行、職場定着フォローアップなど、きめ細かなサポートを無料で受けられます。
3. 地域障害者職業センター:専門的な職業リハビリテーション機関。職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援など、より専門的なサービスを無料で提供しています。
4. 就労移行支援事業所:最大2年間、ビジネスマナーやパソコンスキル、コミュニケーション訓練などを受けながら就職を目指せる福祉サービス。就職後の定着支援も充実しており、多くの方が無料または低額で利用できます。
5. 発達障害者支援センター:発達障害に特化した相談支援機関。診断前の方も相談でき、医療機関や就労支援機関への紹介、特性に合った職種選びのアドバイスを無料で受けられます。
6. 転職エージェント(障害者雇用専門):民間の就職・転職支援サービス。非公開求人の紹介、履歴書添削、面接対策、企業との条件交渉を代行。基本的に無料で利用できます。
自分の状況やニーズに合わせて、これらのサービスを組み合わせて利用すれば、より効果的な就労支援を受けられます。
まとめ
本記事では、発達障害のある方が仕事を見つけ長く働き続けるための情報を包括的に解説してきました。
発達障害はそれぞれ異なる特性を持っています。
自分の特性を理解すれば、適職を見つける第一歩です。仕事が続かない、ミスを繰り返す、コミュニケーションがうまくいかないなどの困りごとは、特性と環境が合っていないために生じています。適切な対処法を知れば改善できる可能性があります。
特性に合った仕事を選ぶのが重要です。職場定着のためには、「コミュニケーションの工夫」「合理的配慮の依頼」「ツールの活用」「ストレス管理」「相談先の確保」という5つの工夫が効果的です。さらに、ハローワーク、就労移行支援事業所、転職エージェントなど、さまざまな就労支援サービスを活用すれば、自分に合った働き方を実現できます。
発達障害があっても、適切な理解と工夫、そして周囲のサポートがあれば、充実したキャリアを築けます。
まずは自分の特性を知る段階から始め、就労支援サービスを活用しながら、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
あなたに合った働き方は必ず見つかります。
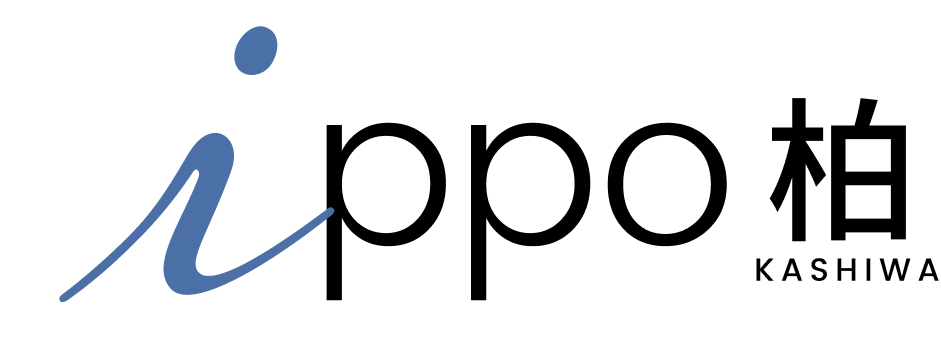

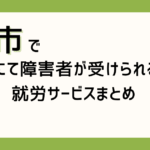



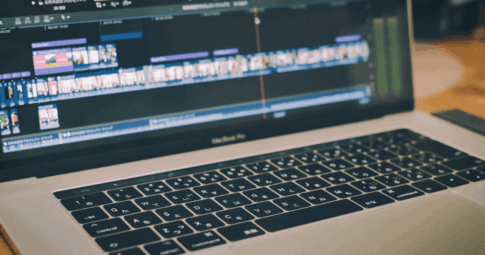
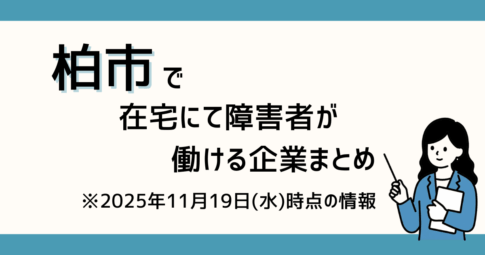


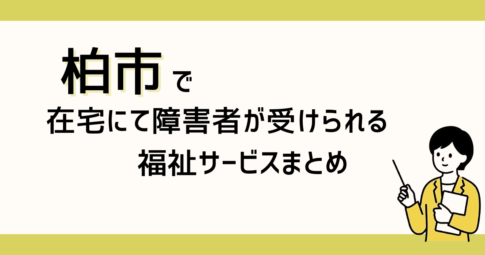
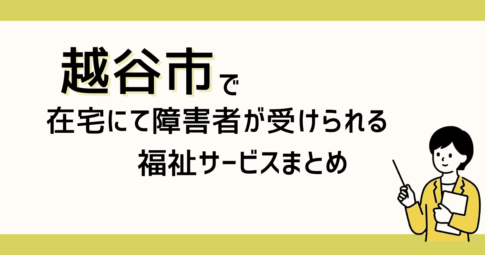
コメントを残す